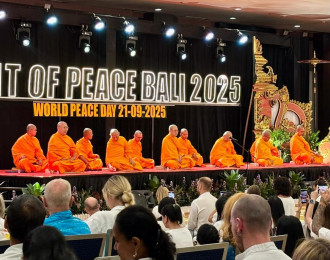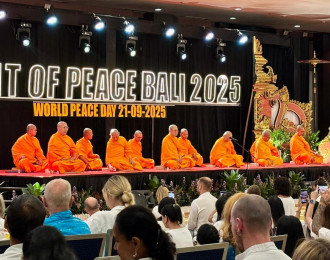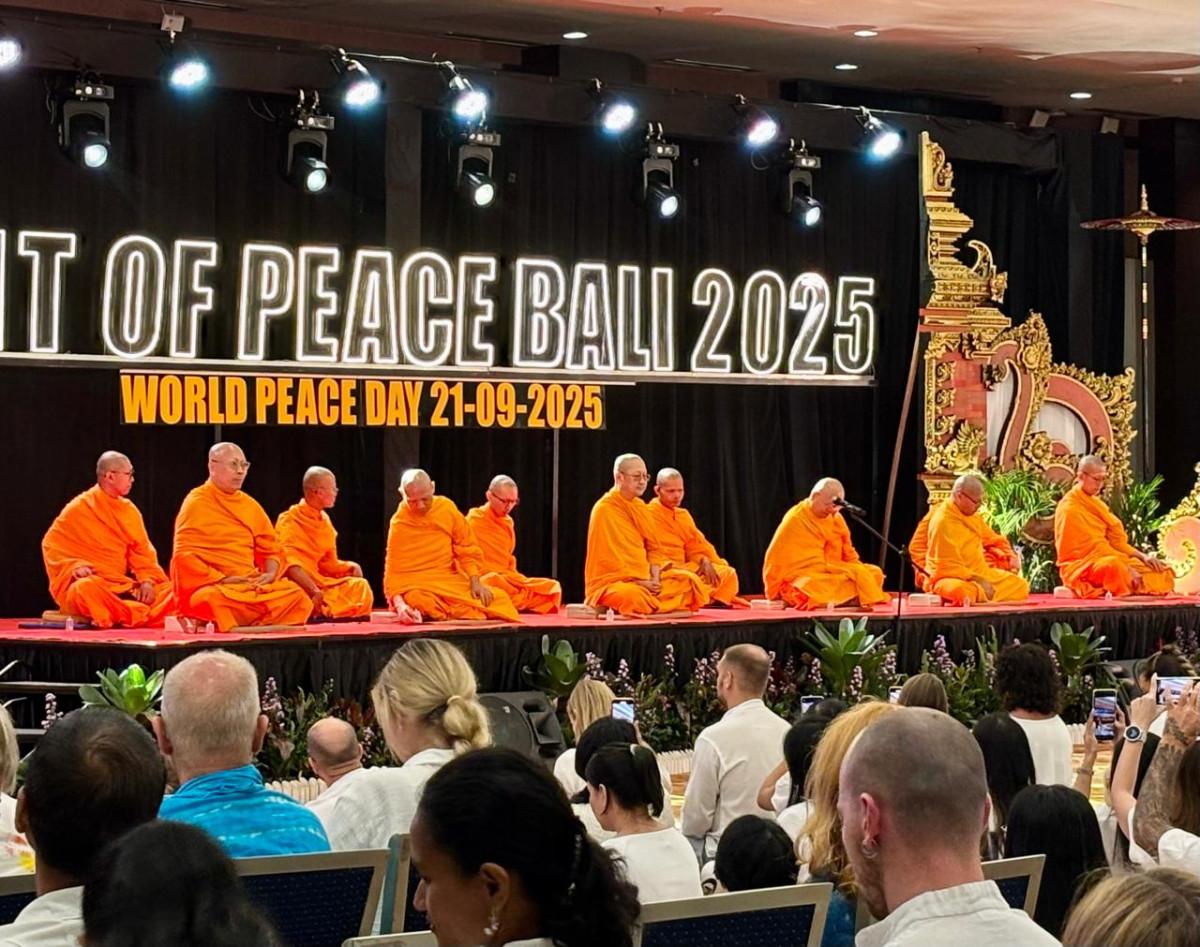バリ島タバナン県のダウプカン国立第4小学校(Jl.Murai Gg. IV No.1, Dauh Peken, Tabanan)で5月22日、JICA草の根パートナー型事業として富山県のNGOである一般社団法人「インドネシア教育振興会」が行っている環境教育のプロジェクト最終段階の視察が行われた。
プロジェクトの実施側(JICA/IEPF)に経過・成果を説明する校長
「えんぴつ一本からできる国際ボランティア」をスローガンに、インドネシアの子どもの教育の振興を第一の目標として2000年4月に設立された同NGO。2010年、インドネシアに現地教育法人を設立し、東ヌサトゥンガラ州クパン市、ティモール島、フローレス島、バリ島で活動している。2014年、2016年に次ぎ、2021年からJICAの協力の下で始まったフェーズ3の環境教育事業では、「SDGsデジタル教育教材開発と教員向けの日本授業研究」をインドネシアの離島の小学校への導入を目的にした。
今回のプロジェクトはインドネシア内の3カ所がモデルエリアとして選ばれたが、使用するデジタル教材は各地域によって違ってくる。
同法人代表理事の窪木靖信さんは「インドネシアはとても広い国で、地域によって特色も環境問題に対しての課題や問題も異なるので、それぞれの地域の特性を生かした教材を作ることで、より自分事として捉え、学べることができるように教材は各地域で制作した。教員には、日本式授業研究を通して教員同志で教え方を学び合ってもらえれば」と話す。
同プロジェクトが最終段階に入っているため、インドネシア振興会の日本人スタッフをはじめ、JICAインドネシアの職員やタバナン県環境課長などが当日、事業の成果を確認するため、全校児童142人が学ぶ同校へ視察に訪れた。
東ヌサンタラ州のモデル地域の小学校では、デジタル環境素材が授業科目の教科として認められ、教科として導入されている。バリ島タバナン県では県内20校がモデル校、40人の教師(1校2名)が指導員となってプロジェクトがめられ、今後はタバナン県教育局とも連携し、県内にある288の小学校で教科として、デジタル教育が行われるという。
一行は同校での視察後、タバナン県知事を表敬訪問した。